インタビューを受けていただいた方

銀行の流動性供給とは何ですか?
銀行の流動性供給とは、銀行がその業務を通じて現金により近い資産を市場に供給することを指します。例えば、銀行が貸出を行うと預金口座に預金が振り込まれ、借り手はそれを使うことができますので、流動性を銀行から得たことになるわけです。ほかにも、銀行は社債や株式を買うことがありますが、こうした取引も流動性の低い資産を引き受け、預金などの流動性の高い資産を受け渡すことで市場に流動性を供給します。
 郡司教授
郡司教授
経済全体のお金を増やす信用創造とはどのような仕組みですか?
簡単に言うと、銀行が貸出などを通じて預金を増やす仕組みが信用創造です。銀行は貸出を主な業務の一つとしていますが、貸出を行う際に元手が何もなくても、借り手の預金通帳に貸出額(例えば1000万円)と記入することで貸出を行うことができます。もちろん借り手が現金を引き出すこともありますので、業務上全く現金が必要ないわけではありませんが、貸出自体には現金は必要ありません。したがって、原理的には銀行は何もないところから預金を生み出しているわけです。このような機能を信用創造と呼びます。
 郡司教授
郡司教授
こう言いますと、銀行はどこまでも信用創造できてしまうと思われるかもしれませんが、そうはなりません。銀行は自己資本比率規制という決まりに従わねばならず、リスクのある貸出を抑える必要があります。また、銀行は儲けを出さねばなりませんから、儲からない貸出はしたくはありません。これらの理由から、信用創造は無限に行えるわけではないのです。
 郡司教授
郡司教授
日本銀行と普通の銀行は、どのような関係にあるのでしょうか?
2つの見方があると思います。1つは、中央銀行のサービスを提供する側と利用する側としての関係です。中央銀行は預金口座(中央銀行当座預金)を銀行に提供しており、銀行はこれを通じて銀行間の決済や政府との決済を行うことができます。日銀当座預金では1日に約200兆円もの決済が行われています。また、銀行は中央銀行から借り入れることもできます。まさに、「銀行の銀行」としての役割が中央銀行にはあります。
 郡司教授
郡司教授
2つ目は、監視する側とされる側としての関係です。中央銀行は金融システムの安定を目標の一つとしていますので、銀行が健全に経営していることを求めます。そこで、中央銀行は銀行に対して考査を行い、経営状況をチェックしています。
 郡司教授
郡司教授
日本の銀行は世界と比べてどのような特徴がありますか?
日本では銀行が企業と包括的かつ長期的な関係を持つメインバンク制という慣行があります。銀行は様々なサービスを企業に提供する一方、企業側は一つの銀行と長期的に取引し、金融市場で資金調達するのではなく銀行借入に頼る傾向があります。近年ではメインバンク制は弱まってきていると言われますが、世界的に見れば、大企業を除いて依然として銀行借入が主な調達先である企業は多いと思います。
 郡司教授
郡司教授
メインバンク制は企業の状態を把握しやすくするため、利子や手数料を安く抑えることを可能にする一方で、経営状態が悪くても貸出を続けることで退出すべきなのに生きながらえるゾンビ企業を生み出す可能性もあり、一長一短と言えます。
 郡司教授
郡司教授
デジタル時代に銀行の役割はどう変化していますか?
電子商取引(EC)の発達により最終的な決済に使われる銀行預金の役割は高まってきています。2024年度は預金の伸びは若干緩まりましたが、依然として重要であることに変わりはありません。企業の資金調達の面でも銀行貸出の比重はやはり大きく、銀行の役割は重要であると言えます。
 郡司教授
郡司教授
他方で、競争環境の激化により銀行の収益源は減ってきています。例えば、様々な電子決済の登場で決済からの手数料は得にくくなりました。今後、デジタル化が進展するにつれて、銀行は業務の多角化を余儀なくされると予想されます。
 郡司教授
郡司教授

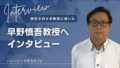
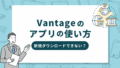
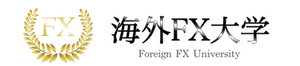
ご意見・ご質問