インタビューを受けていただいた方

コーポレートガバナンスと金融市場は、どのような関係があるのでしょうか?この2つが結びつく理由を教えてください。
コーポレートガバナンスとは、企業統治と訳されることが多く、「企業経営」を外部の出資者の利害に合わせて、適切に行うための仕組みです。株式会社において、外部の投資家は、企業の発行する「株式」を購入することで、「株主」になります。株式会社の経営は、経営のための資金を提供する「株主」の「出資金」を利用して行われるので、「株主」の利害に合う形で、企業経営を行うことが重要になります。
「株主」は、外部の投資家なので、自身の「利害」に合わない経営状況の企業の株式については、いつでも「金融市場」で売却することが出来ます。特に、多くの「株主」が「利害」に合わないと感じる企業の株式は、金融市場で大量に売られるため、「株価」が低迷します。一方で、株主目線の経営が出来ている企業では、多くの投資家が、金融市場で購入するため、株価は上昇します。
「株主」は、外部の投資家なので、自身の「利害」に合わない経営状況の企業の株式については、いつでも「金融市場」で売却することが出来ます。特に、多くの「株主」が「利害」に合わないと感じる企業の株式は、金融市場で大量に売られるため、「株価」が低迷します。一方で、株主目線の経営が出来ている企業では、多くの投資家が、金融市場で購入するため、株価は上昇します。
 坂和准教授
坂和准教授
以上のように、企業の経営者は、金融市場での自社の「株価」を見ることで、「外部の株主の利害にあった経営を行えているか?」を知ることが出来ます。すなわち、金融市場での「株価」の上昇(/下落)は、企業経営者に対して、「コーポレートガバナンスが上手く機能している(/機能していない)」企業であるという金融市場からのシグナル(Signal)と判断できます。このように、コーポレートガバナンスと金融市場は密接に関連しています。
 坂和准教授
坂和准教授
会計不正を防ぐための企業統治の仕組みについて研究されていますが、投資家はどのような兆候に注意し、どう対策すべきでしょうか?
企業の会計不正の問題は、2009年から2014年の東芝の事例のように、日本を代表するような大企業でも起きうる可能性があります。会計不正の場合、企業が外部の株主に公表する決算情報などが不正確であることもあり、外部の投資家がその兆候を知ることは難しいです。東芝のケースでは、銀行融資を受けた際に、「営業利益・企業格付けなどが事前に合意した水準を下回った場合には即時に借入金を全額返済する」という条件(財務制限条項)が附されていたことが、経営陣の不正会計の一つの動機ではないかと言われています。期限前の借入金の全額返済を避けるために、不正会計で「純利益」を一定の水準以上に見せかける必要があったのではないかという推測できます。このような事例を考えると、たとえば財務諸表の注記で、借入金に財務制限条項がついているかどうかを確認することも一つの方法になるかもしれません。
 坂和准教授
坂和准教授
外国人投資家が日本企業の株主になることで、その企業の経営方針や財務戦略はどのように変化するのでしょうか?
外国人投資家は、国内投資家と比べて、投資した「株式」の保有期間が短いことが知られています。したがって、比較的に短い期間での投資先の企業経営の改善(「株価」の上昇)を求めるので、株主総会の場で、経営陣に対して、様々な提案を行うことが知られています。日本の株主総会で、既存の経営方針に対する変化などを求める提案を行うことから、外国人投資家は、「物言う株主」あるいは「アクティビスト(Activist)」と呼ばれることが多いです。
 坂和准教授
坂和准教授
現在の日本の株式市場では、外国人投資家の「持株」比率が上昇しており、企業の経営方針や財務戦略に対して、外国人投資家の与える影響も増していると考えられます。企業の経営方針に関与する例としては、新たな「社外取締役」の選任を求めて、企業経営の変化を起こそうとする事例もあります。たとえば、2023年のフジテック社に対する外国ファンドで大株主のオアシスによる株主提案では、6人の社外取締役の選任を求め、その内、4人の選任が株主総会で認められました。
外国人投資家は、直接的に「株主」としての「利益」を確保したい動機で、配当の増加や自社株買いの実施などの提案することが多いようです。結果的には、財務戦略としては、「純利益」の内、現在の株主に対する「株主還元」に回る資金が増えることで、長期的な視点での「投資」などが抑制される可能性も高いと考えられます。
外国人投資家は、直接的に「株主」としての「利益」を確保したい動機で、配当の増加や自社株買いの実施などの提案することが多いようです。結果的には、財務戦略としては、「純利益」の内、現在の株主に対する「株主還元」に回る資金が増えることで、長期的な視点での「投資」などが抑制される可能性も高いと考えられます。
 坂和准教授
坂和准教授
長期投資を考える際、財務指標とガバナンス指標をどのように使い分けて判断すべきでしょうか?
財務指標は、年次決算(あるいは中間決算)などに基づいて計算するので、投資家にとっては、現状の1年(あるいは半年)などの企業の経営状況を判断することに役立ちます。一方で、ガバナンス指標は、直近の企業利益あるいは財務指標を改善することに直結するかは分からないですが、長期的には企業経営を改善する要因と考えられるため、「より長いスパンで、投資を考える企業の経営状況が改善するか?」についての判断材料として役立つといえるでしょう。
 坂和准教授
坂和准教授
コーポレートガバナンス×金融の研究分野において、今後注目すべきトレンドや研究テーマは何でしょうか?
コーポレートガバナンス×金融の分野は、①で述べたように密接に関連しています。昨今の「コーポレートガバナンス」改革は、取締役会メンバーの多様性を推進する方向で進んでいます。企業の内部の経営者が、外部の株主の利害に反する形で経営を行わないようにするためには、企業経営の最終的な意思決定を行う「取締役会」に、内部経営者と独立した「社外取締役」の選任が重要と言われてきました。近年では、それに加えて、そもそも取締役会メンバーの多様性が重要視されています。
このようなコーポレートガバナンス改革の下で、女性取締役の登用が少しずつ進んでいる状況です。たとえば、「女性取締役の登用が、企業経営にどのような影響をあたえるのか?また、その影響は、金融市場でどのように評価されるか?」といった点についてはまだまだ解明されていない状況です。このようなテーマでの研究が今後進んでいくのではないかと考えています。
このようなコーポレートガバナンス改革の下で、女性取締役の登用が少しずつ進んでいる状況です。たとえば、「女性取締役の登用が、企業経営にどのような影響をあたえるのか?また、その影響は、金融市場でどのように評価されるか?」といった点についてはまだまだ解明されていない状況です。このようなテーマでの研究が今後進んでいくのではないかと考えています。
 坂和准教授
坂和准教授
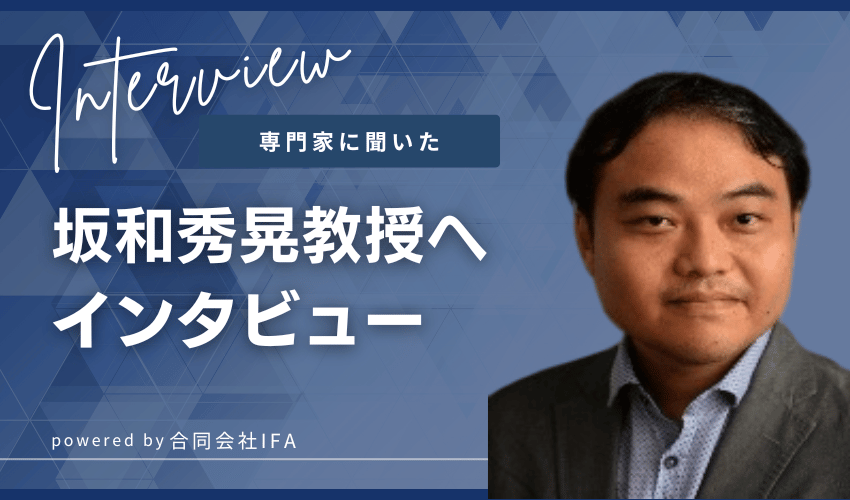

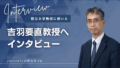
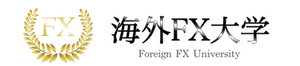
ご意見・ご質問